採用広報の飯野です。
今回はオンライン決済サービス「PAY.JP」のプロダクトチームが取り組んだ「3Dセキュア導入プロジェクト」の話題です。
前編では、プロジェクトの全容についてお聞きし、APIサービスに携わる魅力や難しさを語っていただきました。
後編では、「PAY.JP」で働く魅力にフォーカスしました。
インタビュイーの3名は、2010年代後半から10年近く「PAY.JP」に携わり、ひとつのサービスに長く携わる魅力について「自分が作った負債を自分で返すチャンスがある」と話します。
ぜひ最後までご覧ください。
【Profile】
写真左:野見山 志帆(のみやま しほ)
PAY株式会社 Product Division Product Management
新卒ではカード会社に総合職として入社。その後、外資の動画配信会社へ日本法人の立ち上げ期に転職し、3社目ではネット証券会社でCSや事業推進を経験する。CSの立ち上げにチャレンジしたいという思いから、2018年7月にPAY株式会社にCSとして入社し、マネージャーを経てチーム内初となるProduct Management(以下、PdMと表記)にジョブチェンジ。
写真中央:東 健太(あずま けんた)
PAY株式会社 CTO
新卒で携帯アプリの開発会社に入社後、受託開発会社にて開発業務に従事。その後、「開発を手がけたサービスに責任を持ちたい」という理由から、2016年7月にBASE株式会社 PAY.JP Division(当時)にインフラエンジニアとして入社。その後テックリードを経て2023年にPAY株式会社のCTOに就任。
写真右:山中 夏樹(やまなか なつき)
PAY株式会社 Dev Division エンジニア
新卒では携帯アプリの開発会社に入社し、Perlのサーバーサイドエンジニアから業界経験をスタート。その後、アプリの受託開発会社に転職しNode.jsを使ったチャットサービスやWebRTCを使った通話機能の実装などを経験。2017年12月にBASE株式会社 PAY.JP Division(当時)にアプリエンジニアとして入社。現在は、サーバーサイドエンジニアに転向。
長期でひとつのサービスに携わる魅力は「自分の負債を返すチャンス」があること
皆さんはコロナ前からオンライン決済サービス「PAY.JP」の開発に携わっているのですね。
東: そうですね。私がBASEグループに入社した当時は、まだPAY株式会社として分社化する前で、BASE株式会社のPAY.JP Divisionという1部署でした。
山中: 僕はPAY株式会社が設立された2018年1月にBASEグループに入社したんです(笑)設立と同日ですね。
野見山: 私は山中さんのすぐ後に入社したので、会社になったばかりのタイミングでした。当時の社員数は15人くらいで、今を比べると結構変わったなと感じます。当時は強い個人が同じ場所に集まっているという感じでしたが、現在は組織としてのまとまりが出てきて、情報の流通や意思決定がしやすくなったなと思います。
東:
取り扱う金額も桁が変わるほど大きくなりました。
ただ個人的な感覚としては、やっていることは9年前と変わっていないなと思います。というのも、インフラ部分の初代、2代目、現在の3代目と置き換えを僕が主導してやってきていたりするので、変わったなと客観視するというよりは頑張ったなという感覚が強いです。

そうなのですね。「PAY.JP」の魅力について教えてください。
野見山: 「PAY.JP」の純粋なおもしろさは、決済事業であるというところです。決済はどのビジネスにおいても根幹だと思うので、その部分を支えることができているのはやりがいがありますね。たとえば、審査の申請が来る加盟店さんのサービスを見ていると、「今はこういうスキームのサービスが多いんだな」と新しいビジネススキームを知ることができたり、「加盟店さんはこういったところで困るんだな」と解消すべき部分を知れたりとさまざまな学びがあります。
APIサービスを利用する加盟店さんの先にもさらにお客様がいるというのは、目に見えない部分が多く大変ですが、勉強になります。
ひとつのサービスに長く携わる魅力はどんなところにありますか?
野見山: 過去の自分が作ってしまった負債と向き合い、自分が解消する場面が訪れることです。その経験で強くなれるというのが私は魅力だと思います。
あとは、決済のことに詳しくなって、話せる相手が増えるのがおもしろいなと思っています。これまでの会社は2〜3年で転職していたので、1つの事業に詳しくなることはあまりなかったんですよね。上位のレイヤーの方とも解像度高く話せるようになるので、入社当時は東さんが言っていることは20%くらいしかわからなかったんですが、今では解像度100%で話せるようになりました(笑)
東:
「負債と向き合わないといけない」という話が野見山さんからありましたが、過去の受託開発の経験から思うのは、エンジニアとして自分の作った負債を自分で返せるチャンスって意外とないんですよ。自分が一生懸命作り込んだサービスでも、退職、サービス終了、契約終了、工数がもらえないといったさまざまな理由から、フィードバックを得てそれを反映させて改善する機会が得られないことが多かったです。
でも長年同じサービスに携わっていると、自分の負債を自分で返すチャンスがあるんです。そしてそういった経験をしていると、最初に作るときに数年後の未来を考える力がつくように感じます。もちろん未来はわからないことだらけですし、実際は今書いたものは5年後には古くなって捨てたくなるんでしょうけど、それでも自分で返すチャンスがあるというのは、大きな魅力だと思います。

山中: 長く携わったことでいろんな実装や障害を経験してきたので、その経験を生かして会社やチームの求めることに応えていくのはやりがいがあります。 長年携わっていますが、サービスの成長や世の中の変化にあわせて会社からの要望もどんどん出てきます。求められることは尽きません。そこに応え続けていくのは楽しいです。
責任の幅が広い人材を求める
皆さんはどんな方と一緒に働いてみたいですか?
東: 「責任の幅が広い人」ですね。
野見山: そうじゃないとなかなか難しいですよね。
東: はい。もちろん何でもできる人は理想ではあるんですけど(笑)「線」を引かないというのは大事だと思います。少なくとも隣り合っている領域に興味を持って欲しいです。隣り合っているということは、自分の仕事をうまく進めるために必要なことがあるわけじゃないですか。その部分に積極的に知識を得ようとしたり関わったり協力してくれる人と一緒に働きたいなと思いますね。
野見山: 実は私たちはプロジェクトを進めるときに、明確に役割をわけているわけではないんですよね。たとえば「あ、山中さんがここまで進めてくれたんだ!」といったこともよくあります。領域を自分で決めずに興味を持っていろいろとチャレンジしてくれる方がありがたいなと思います。
山中: 今の「PAY.JP」はまだそこまで大規模な組織でもないと思うので、広い働き方ができると思っています。開発職は与えられる裁量が大きいなと感じます。「Focus on Impact(※1)」という行動指針があり、言ってしまえば成果が出るなら自由にトライしようという文化なので、言われたことをやるだけではなく、自分から前のめりに動きたい方には向いていると思います。
(※1)「Focus on Impact」の説明について詳しくはこちらを参照https://note.com/base_group/n/n895e9dbcbbc7
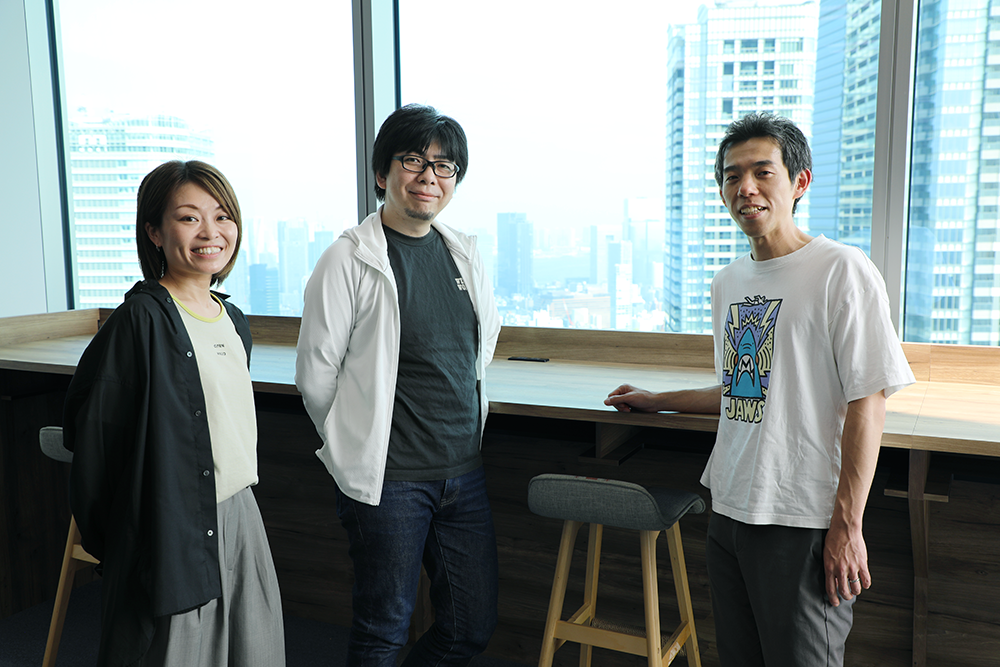
最後に
「お客さんの、お客さんまでユーザー体験を考えながら、今使っている人が困らないように、より良いプロダクトへと変えていく」
言葉にするのは簡単ですが、実現するのは容易ではありません。「自分の負債を自分で返す」経験を積み重ねてきた3名だからこそ、未来を見据えた質の高いプロダクト開発ができるのだと感じました。
◆PAY.JP 求人はこちら open.talentio.com


